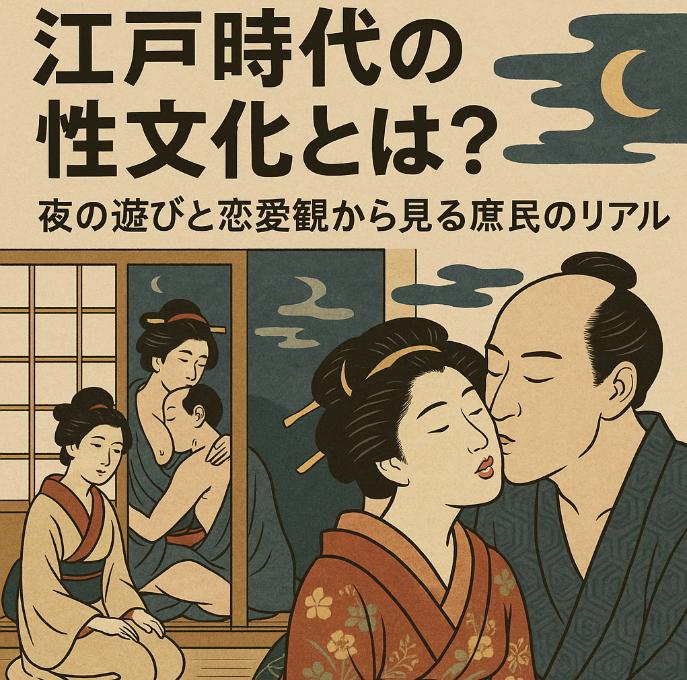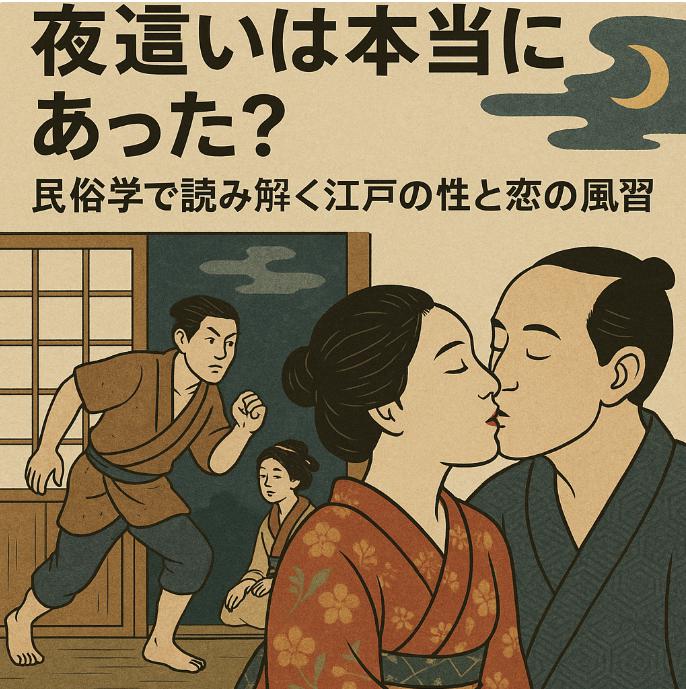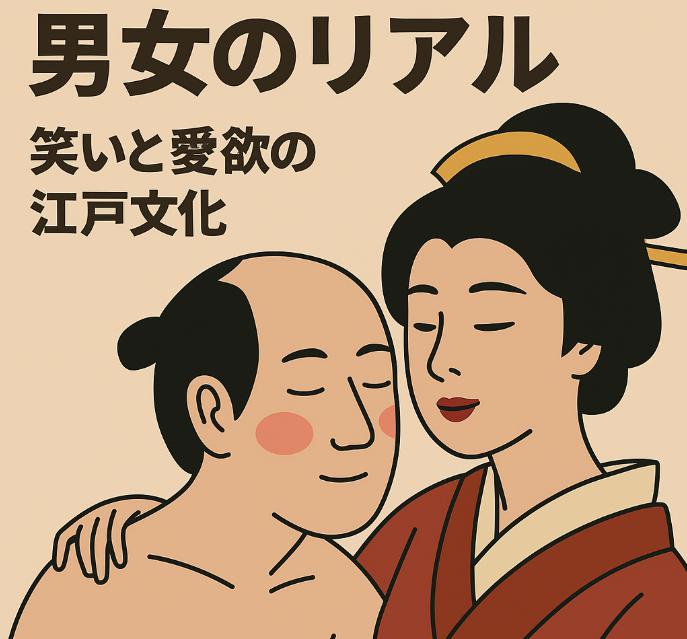「夜這い」と「通い婚」はどう違うの?
どちらも「男性が女性のもとに通う恋愛文化」ですが、この2つには明確な違いがあります。
- 夜這い:主に未婚男女の恋愛や性交渉のきっかけ。地域によっては“お試し交際”のような位置づけ。
- 通い婚(妻問婚):結婚成立後、夫が妻の実家に通う正式な婚姻形態。日中は実家、夜だけ妻宅へ通うスタイル。
つまり、夜這いが「恋のはじまり」なら、通い婚は「結婚後の新しい夫婦生活」というわけです。
この“通う”という行動に、江戸時代の恋愛と結婚の価値観がギュッと詰まっています。
通い婚とは?妻が実家にいるまま夫が“通う”結婚形態
通い婚(妻問婚)とは、夫が妻の家に通って一緒に夜を過ごす婚姻形式のことです。
夫婦が同居しないのが最大の特徴で、特に以下のようなケースで通い婚は一般的でした:
- 経済力のない若夫婦(妻の実家で生活支援を受ける)
- 長男以外の次男・三男(本家を継げないため婿入りせず)
- 嫁入りの風習がなかった村や地域(西日本に多い)
つまり、「結婚=同居」という固定観念がなかったのです。
現代の“別居婚”にも通じる柔軟な結婚スタイルですね。
- 夜這いは“お試し交際”だった?──結婚前の関係構築
一方、夜這いはあくまで未婚の男女間の恋愛的交流です。
「通って関係を持つ」という意味では通い婚に似ていますが、法的・社会的に結婚が成立していない点が大きな違いです。
夜這いの目的は、
- 男女がお互いを見極める
- 相性を確認する(身体的な意味も含め)
- 婚約の前段階として親に認めてもらう
など、現在で言う“真剣交際”に近いものでした。
逆に、3日続けて女性が受け入れれば、事実上の婚約成立とみなされる地域もありました。
家制度がなかったからこその「通い文化」
江戸時代は今ほど“家”の制度が確立していなかったため、結婚や夫婦のかたちも地域ごとに多様でした。
- 男が女の家に入る「婿入り」
- 形式上結婚しても別居する「通い婚」
- 恋愛から自然発生的に夫婦になる「夜這い婚」
これらは、今の“届け出婚”“事実婚”“内縁関係”のような、柔軟でバリエーション豊かなスタイル。
「結婚とはこうあるべき」という縛りが弱かったからこそ、人々は恋愛も性も、もっと自然体で受け入れていたのかもしれません。
女性の意思がカギだった通い文化のリアル
ここで見逃してはいけないのが、女性の意思が非常に重要だったという点です。
夜這いも通い婚も、女性が拒否すれば関係は成立しない、という暗黙のルールがありました。
家族もそれを知っていて、娘の意志を尊重するケースが多かったのです。
さらに、通い婚の関係では、女性側の家が夫を「迎える」立場。
夫が失礼な態度を取ったり、粗相があれば、女性側が関係を断つこともできました。
つまり、表面的には男性主導のように見えて、実は女性にとって主導権のある結婚スタイルでもあったのです。
通い婚が消えた理由:制度の画一化と「嫁入り文化」
明治以降、戸籍制度や法律の整備とともに、結婚=「同居・嫁入り」が当たり前の時代になります。
- 妻は夫の家に入る「嫁入り婚」へ一本化
- 戸主制度の導入で“本家”重視の文化が拡大
- 都市化によって「親元で暮らす」ことが難しくなった
その流れのなかで、夜這いも通い婚も、「非正規」「旧時代的」として廃れていったのです。
現代ではあまり語られない通い文化ですが、かつての日本にはこんなにも柔らかく、個人の感情に寄り添った結婚のかたちが存在していたのです。
まとめ:夜這いと通い婚は「恋と結婚」の自然な流れ
・夜這い=恋愛・交際の入り口、通い婚=結婚後の夫婦形態
・女性の意思と地域の風習が関係性を決めていた
・制度に縛られない柔軟な婚姻文化が存在していた
・明治以降、制度と道徳の画一化により消滅